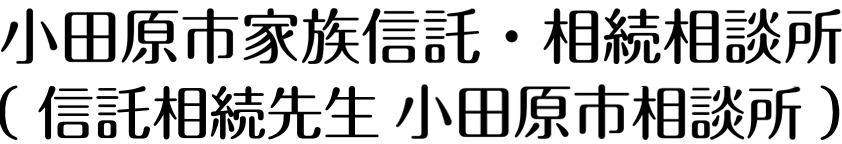相続税申告は自分でできる?手続きの流れと専門家に依頼するメリット
- 公開日:
- 更新日:
はじめに
親の相続が発生したとき、「相続税の申告を自分でできるだろうか?」と悩む方も多いでしょう。本記事では、ご自身で相続税申告を行う場合の基本的な手続きの流れと、その際に注意すべきポイントを解説します。財産目録の作成から申告書提出までのステップを説明するとともに、税理士など専門家に依頼するメリットについても紹介します。申告業務を自分で行うべきか、それとも専門家に任せるべきか判断に迷う方は、ぜひ参考にしてください。
自分で相続税申告を行う際の基本手続き
相続税申告を自力で行う場合、以下のような基本的なステップを踏むことになります。各ステップを順を追って見ていきましょう。
財産目録の作成(資産・負債の洗い出し)
まず最初に、被相続人(亡くなった方)が残した財産目録を作成します。プラスの財産としては、預貯金残高や不動産、株式、投資信託、自動車、美術品、生命保険金など多岐にわたります。一方、マイナスの財産として借入金(住宅ローンやカードローン)、未払いの医療費・税金なども洗い出します。相続税の計算では、これら資産と負債をすべて合算した正味の遺産額を把握する必要があります。
この段階では、通帳の履歴や証券会社の残高証明、不動産の権利証・固定資産税通知書など、あらゆる資料をかき集めてリスト化する作業が中心です。例えば、小田原市のCさんは父親の相続で財産調査を行った際、父親名義の銀行口座が複数あることや、過去に購入した投資信託が判明しました。このように、見落としのないよう徹底的に調べることが重要です。
各資産の評価額算出と相続税額の試算
財産目録が完成したら、次に各資産の評価額を計算します。不動産であれば路線価評価額、上場株式であれば死亡日の終値や平均株価などで評価します。預貯金はその残高、生命保険金は非課税枠(法定相続人×500万円)を考慮して課税対象額を算出します。一通り評価が終わったら、遺産総額(債務控除後の正味遺産額)が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるか確認しましょう。超えていれば相続税の申告が必要となります。
申告が必要な場合、税率表を使って相続税額の試算を行います。法定相続分に応じた取得額ごとに課税される仕組みを踏まえ、まず相続税の総額を計算し、そこから各相続人の実際の取得財産に按分して税額を見積もります。初めての方には少し複雑ですが、国税庁のホームページで提供されている相続税の計算ソフトや民間のシミュレーションツールを活用すると良いでしょう。
相続税申告書の作成と税務署への提出方法
評価額と税額の試算ができたら、相続税申告書を作成します。申告書は全20枚ほどの用紙で構成され、主なものに「第1表(相続税の総額等)」「第2表(遺産の明細)」などがあります。各財産の明細や各種控除の適用状況、各人の納付税額などを記入していきます。
申告書の記入が終わったら、管轄の税務署に提出します。提出方法は持参のほか、郵送や電子申告(e-Tax)も可能です。提出期限は被相続人の死亡から10か月以内ですので、期限内に必着で提出しましょう。また、納税が発生する場合は原則として申告期限までに現金一括納付となります(延納を利用しない場合)。納税は金融機関や税務署窓口のほか、インターネットバンキング等による電子納税も可能です。
自分で申告する場合の注意点
自分で相続税申告を行う際には、いくつか注意すべき点があります。専門家の目が入らない分、ミスや漏れが生じやすいため、以下のポイントに気を付けましょう。
複雑な財産評価や特例適用漏れによる申告誤りのリスク
相続税の計算には、不動産評価の特例(小規模宅地等の評価減)や、配偶者控除・未成年控除など多数の特例制度があります。これらを適切に適用しないと、本来より多く税金を支払ってしまう可能性があります。逆に、制度を知らずに誤って適用せず放置すると、後で税務署から指摘を受け追徴課税となるリスクもあります。
例えば、賃貸アパート経営をしていた親の相続では、小規模宅地特例により貸付事業用宅地の評価額を50%減額できる場合があります。しかし知識がなければこの特例を見逃し、大幅に過大な評価額で申告してしまう恐れがあります。また、非上場株の評価や土地の評価などは専門知識が要求され、自分だけでは適正な評価が難しいケースもあります。複雑な財産を含む場合、申告内容に誤りが生じるリスクが高いことを認識しましょう。
必要書類の収集や書類不備による手続き遅延に注意
相続税申告には多くの書類が必要であることは前述しましたが、こうした必要書類の収集も自分で行う場合は負担になります。特に戸籍謄本や残高証明書、不動産の評価証明などは取得に時間がかかる場合があります。また、書類の不備(例えば戸籍が一部不足して法定相続人が確定できない等)があると、申告書を受理してもらえなかったり、手続きが遅延したりします。
自分で進める場合は、早い段階で必要な資料のリストアップを行い、順次取り寄せましょう。提出前には書類が揃っているか丁寧にチェックし、不備がないようにします。期限ギリギリになって書類不足に気づくと大変ですので、時間に余裕をもって準備することが大切です。
相続人間での情報共有不足が招くトラブル防止
申告書の作成は一人でできますが、相続は複数の相続人が関わる共同作業でもあります。相続人同士で財産情報を共有しないまま進めてしまうと、後から「その財産の存在は知らなかった」「遺産分割の内容に納得していない」といった不満やトラブルが生じる可能性があります。
例えば、遠方に住む兄弟に一部の財産情報が伝わっておらず、申告後になって別の預金口座が見つかった場合、再計算や修正申告が必要になるだけでなく、親族間の信用関係も損なわれかねません。自分で申告手続きをする場合でも、相続人全員で情報をオープンにし、協力して進めることが大切です。必要に応じて家族会議を開き、財産リストを共有しながら進めましょう。
税理士など専門家に依頼するメリット
続いて、相続税申告を税理士などの専門家に依頼した場合のメリットを見ていきます。専門家に任せることで得られる利点は多く、手数料がかかるものの、それを上回る安心感や節税効果が期待できることもあります。
適切な節税アドバイスと控除漏れ防止による税額軽減
相続税専門の税理士に依頼すれば、最新の税制や特例の知識を駆使した節税アドバイスを受けられます。例えば、先ほど述べた小規模宅地特例や配偶者控除はもちろん、生前贈与の持戻し調整や二次相続まで見据えた分割方法など、素人では気付きにくいポイントまで考慮して申告書を作成してもらえます。
結果として、利用可能な控除や特例の漏れが防止され、余計な税金を支払わずに済みます。特に相続財産が多額で税率が高くなるケースでは、専門家の節税ノウハウによって数百万円単位で税額が軽減されることも珍しくありません。税理士は「税金のプロ」として、依頼者にとって最適な申告となるよう尽力してくれるでしょう。
煩雑な手続きや書類作成を任せられ精神的負担を軽減
相続税の申告準備から書類作成、税務署対応までのプロセスは、相続人にとって大きな精神的・時間的負担となります。専門家に依頼すれば、そうした煩雑な手続きを一任できるため、ご遺族は他の大切なこと(故人の供養や遺品整理、今後の生活設計など)に注力できます。
特に、ご自身が仕事で忙しい場合や遠方に住んでいる場合、相続のために役所や銀行を回ったり書類を整えたりするのは一苦労です。税理士に依頼すれば、面倒な手続きや書類作成、税務署とのやり取りも代行してもらえるため、相続手続き全般に対する心理的プレッシャーが大幅に軽減します。「初めてのことで何をしたら良いか分からない」という不安から解放され、安心して相続を進められるでしょう。
万一税務調査が来ても専門家が対応し安心
相続税の申告後、税務署から税務調査が入るケースがあります。自分で申告した場合、調査の連絡が来ると「何か間違っていただろうか?」と不安になるものです。税理士に依頼していれば、税務調査への対応も基本的に税理士が立ち会い、窓口となってくれます。
税理士は事前に申告内容を説明できる資料を準備し、指摘を受けそうなポイントも把握しています。仮に申告漏れ等が発覚した場合でも、専門家が適切にフォローし、修正申告や追納手続きまでサポートしてくれるので安心です。特に資産家の方など調査リスクが高いケースでは、最初から専門家に任せておくことで**「いざという時」の心強さ**が得られます。
専門家に依頼する際の費用と選び方
専門家に相続税申告を依頼する際の費用相場や、信頼できる税理士の選び方についても確認しておきましょう。
相続税申告を税理士に依頼する場合の費用相場
気になる税理士報酬ですが、相続税申告の場合、その費用相場は遺産総額の0.5%〜1.0%程度と言われます。例えば遺産総額が1億円であれば、税理士費用は約50万〜100万円ほどが目安です。ただし、財産の種類や難易度によって加算料金が発生することもあります。土地や非上場株式が多いケース、相続人が多数いるケースでは手続きが複雑になるため、報酬が1%を超えることもあります。一方、遺産が比較的小規模(例えば5,000万円以下)であれば、最低料金○万円〜と定額で受け付けている税理士事務所もあります。
誰が費用を負担するかについては相続人間で取り決めが必要ですが、遺産から支払う(相続財産から控除する)ことも認められています。費用に不安がある場合でも、初回相談は無料という事務所も多いので、一度見積もりを取ってみると良いでしょう。
信頼できる専門家を選ぶポイント(実績や報酬体系の確認)
税理士にも得意分野があります。相続税申告を依頼するなら、相続に強い税理士を選ぶことが肝心です。選ぶ際のポイントとしては:
- 実績や専門性:過去にどれくらい相続税申告を手掛けているか、相続関連に精通した資格や研修受講歴があるか。
- 料金体系の明確さ:ホームページや事前説明で報酬基準が明示されているか。追加料金の条件なども含め透明性が高いか。
- コミュニケーション:問い合わせへの対応が迅速丁寧か、こちらの話を親身に聞いて的確な提案をしてくれるか。
例えば、小田原市家族信託・相続相談所には相続専門の税理士が在籍しており、地元での豊富な申告実績があります。また、料金も相続財産の規模に応じた明確な基準を設け、初回の無料相談で見積もりを提示しています。信頼できる専門家を選ぶことで、安心して任せることができ、結果的に円滑かつ有利な相続税申告につながるでしょう。
まとめ:自分で申告するか専門家に任せるかの判断基準
相続税申告を自分で行うか、それとも専門家に依頼するかは、相続財産の内容やご自身の知識・状況によって異なります。比較的シンプルな財産構成で、ご自身に時間と知識があり、費用を抑えたい場合は自分でチャレンジする選択もあります。ただし、少しでも不安がある場合や、財産が多岐にわたる場合、税理士など専門家の力を借りるメリットは大きいと言えます。
大切なのは、相続税申告を正確かつ期限内に済ませることです。そのために必要なら専門家のサポートを受け、円満に相続手続きを完了させましょう。小田原市家族信託・相続相談所では、地元の皆様の相続手続きを丁寧に支援していますので、お気軽にご相談ください。
家族信託・相続のご相談は小田原市家族信託・相続相談所へ
相続税申告を自分で行う際の手順と注意点、そして専門家に依頼するメリットについて解説しました。小田原市家族信託・相続相談所では、相続税の申告サポートから生前対策のご提案まで、経験豊富な税理士が初回無料でご相談に応じます。ご不安な点はぜひお気軽にお問い合わせください。