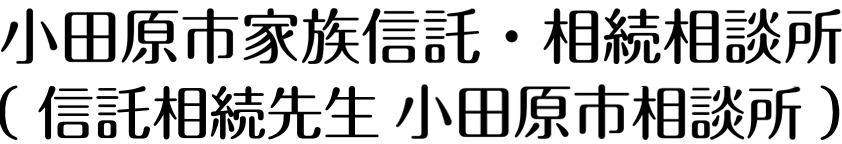生命保険や不動産活用は相続税対策になる?その他の節税策と注意点
- 公開日:
- 更新日:
はじめに
相続税を軽減するための対策にはさまざまな方法がありますが、生命保険の活用や不動産への資産組み換え、借入金の利用といった手法も有効な節税策として知られています。本記事では、生命保険による非課税枠の活用、不動産を使った相続税評価額の引き下げ、借入金戦略や二次相続を見据えた対策など、主な節税策とその注意点を解説します。それぞれの方法が相続税対策としてどう有効かだけでなく、リスクやデメリットにも触れ、ご家庭に合った対策を検討する際のポイントを示していきます。
生命保険を活用した相続税対策
生命保険は、相続税対策として非常に有用な手段です。被相続人が契約していた死亡保険金には、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。例えば相続人が配偶者と子2人で計3人なら、死亡保険金のうち1,500万円までが非課税となり、相続税の課税対象から除外されます。
この非課税枠を利用することで、現金で残した場合には課税される財産も、生命保険金として受け取ることで一定額まで税金をかけずに済ませられます。特に金融資産が多い方の場合、生命保険に資金を振り向けておくことで500万円×相続人の分だけ相続財産を圧縮する効果が得られます。
加えて、保険金は受取人固有の財産として受け取れるため、相続開始直後の生活費や葬儀費用、あるいは相続税の納税資金としてすぐに活用できる点もメリットです。遺産分割協議を経なくても支払われるので、手続き的にもスムーズです。
保険料の負担者を工夫して所得税非課税枠も活用
生命保険を使った節税策としては、契約者や保険料負担者を工夫することで相続税ではなく所得税(一時所得)の課税扱いにできるケースがあります。例えば、子が契約者(保険料負担者)となり、親を被保険者、子を受取人とする契約にすると、親の死亡により子が受け取る保険金は一時所得となります。一時所得は50万円の特別控除があり、さらに課税対象額の1/2が課税所得に算入されるため、相続税より低い負担で済む可能性があります。
ただし、このような契約形態は税務上の取り扱いが複雑で、状況によっては贈与税や所得税の課税関係で注意が必要です。保険料負担者を変更する際には、事前に税理士等に相談して最適なプランかどうか確認することをお勧めします。
不動産の活用による相続税対策
資産を現預金から不動産に組み換えることも有力な相続税対策です。不動産の相続税評価額は、土地であれば路線価もしくは固定資産税評価額、建物であれば固定資産税評価額といった具合に計算され、多くの場合実際の時価より低めに算定されます。そのため、現金で持っているより不動産として持っていたほうが評価額を下げられる場合があります。
評価額の低い不動産への資産組み換え(現金→不動産)
例えば、5,000万円の現金をそのまま相続すると5,000万円が課税対象になりますが、5,000万円で小田原市内の不動産(土地・建物)を取得した場合、相続税評価額は路線価や固定資産評価額ベースとなるため、実勢価格より低く見積もられることが期待できます。ケースにもよりますが、評価額が7〜8割程度に圧縮されることも珍しくありません。
さらに、賃貸用不動産を取得すると、建物は借家人がいることで評価額が3割減され(借家権割合の控除)、土地も借地権や借家権付きの土地(貸家建付地)として評価額が低減されます。こうした仕組みを利用すれば、現金を賃貸マンションやアパートに変えることで、評価額を大幅に下げつつ家賃収入を得ることも可能です。
賃貸物件や小規模宅地特例の活用で評価減を図る
不動産を既に所有している場合でも、小規模宅地等の特例が適用できないか検討しましょう。例えば被相続人が住んでいた自宅の土地(特定居住用宅地)は、配偶者や同居の子が相続する場合に330㎡まで評価額を80%も減額できます。また、貸付事業用宅地(例えば被相続人が貸家として使っていた土地)も200㎡まで50%の評価減が可能です。これらの特例が適用されると、相続税の課税価格を大幅に圧縮でき、納める税金がゼロになることもあります。
ただし、不動産は現金と違ってすぐ売れない、維持管理に手間や費用がかかるなどのデメリットやリスクもあります。賃貸物件なら空室リスクや建物の老朽化、地震などの災害リスクも考慮しなければなりません。相続税の節税効果とこれらリスク・コストを天秤にかけ、総合的に判断することが大切です。
借入金を利用した節税策の考え方
相続税の計算では、被相続人の債務(借入金)は遺産総額から差し引くことができます。この仕組みを逆手に取り、あえて借入金を作って純資産を圧縮するという節税策も存在します。
あえて借入をして純資産を圧縮するメリット・デメリット
例えば、多額の現金をお持ちの方が、あえて銀行から借入をして賃貸ビルを建設したり、高額の生命保険に一時払いで加入したりするケースがあります。借入金は債務として相続財産から控除できますし、借入で取得した不動産には前述の評価減効果も期待できます。また、借入金の利息は不動産所得と相殺されるため、所得税・住民税の節税につながる場合もあります。
ただし、この方法は借金を残すリスクと表裏一体です。賃貸経営が順調にいけばよいですが、もし空室が埋まらなかったり不動産価格が下落したりすると、借金だけが残ってしまう可能性もあります。過度に借入を増やしすぎると、相続人に大きな負担を強いる結果にもなりかねません。
過度な借入のリスクと返済計画の重要性
借入金を利用した節税策を取る場合は、返済計画や出口戦略を十分に考慮することが不可欠です。たとえ相続税が節約できても、残されたご家族が借金の返済に苦労するようでは本末転倒です。リスクシナリオも想定し、最悪の状況でも対処可能な範囲内で借入を利用するよう心掛けましょう。
実際にバブル期には、多額の借入で投資を行ったものの、その後の地価下落で資産価値が下がり、相続時に大変な思いをしたケースも報告されています。借入を使った対策は高度なプランニングが必要なため、必ず税理士やFPなど専門家とシミュレーションを重ねながら進めてください。
二次相続まで見据えた相続税対策
相続税対策を考える際、二次相続(配偶者から子への相続)まで視野に入れることが大切です。一次相続(例えば夫から妻への相続)では配偶者控除で税金ゼロになったが、妻が亡くなったとき(二次相続)に子が多額の遺産を一度に相続することで、最終的な税負担が大きくなる──これはよくあるパターンです。
一次相続で配偶者だけでなく子へ分配し税負担を平準化
この問題に対処するため、一次相続の時点で子にもある程度遺産を分けておく方法があります。配偶者が取得する財産を抑える代わりに子が相続税を少し負担する形ですが、その分二次相続時の課税財産が減り、結果として一次・二次合計の税額が少なくなる可能性があります。
例えば、配偶者が全財産を相続した場合は一次相続で税金ゼロ、二次相続でまとまった遺産に高い税率が適用されるかもしれません。しかし、一次相続で子が相続してある程度税金を払っておけば、二次相続時には残された財産が小さくなり税率区分も低く抑えられるため、二度の相続税の合計が圧縮される効果が期待できます。
もちろん、この判断にはご家族の年齢構成や資産規模、ライフプランなども関係します。配偶者が高齢で、あまり時間を置かず二次相続が起こりそうな場合は特に有効ですが、慎重なシミュレーションが欠かせません。
生命保険の受取人や契約者を調整し二次相続時の非課税枠を確保
生命保険を活用して二次相続対策をすることも可能です。一次相続時に配偶者が保険金を受け取る契約になっていた場合、配偶者は非課税で受け取れます。その後、配偶者が契約者となって子を新たな受取人に変更しておけば、配偶者の死亡(二次相続)の際に子が再度500万円×法定相続人分の非課税枠を利用できます。
例えば、夫が加入していた生命保険(夫が契約者・被保険者、妻が受取人)があったとします。夫死亡時、妻が保険金を受け取ります(配偶者なので相続税非課税)。その後、妻が契約者として同じ保険契約を継続し、受取人を子に変更すると、妻死亡時には子がその保険金を受け取り、今度は子に対して法定相続人×500万円の非課税枠が適用されます。こうすることで、一つの保険契約で二度非課税枠を利用できたことになります。
ただし、契約者変更は保険会社への手続きが必要なだけでなく、場合によっては贈与と見なされるリスクもあります。安易に変更せず、税理士や保険外交員などの助言を受けながら適切に行ってください。
各種対策を講じる際の注意点
ここまで生命保険、不動産、借入金、二次相続対策と多様な節税策を述べてきましたが、どの対策も万能ではなく、注意すべき点があります。 最後に共通する注意事項を整理します。
節税策に伴うリスク(流動性の低下や維持費用など)
節税のために資産構成を変えると、流動性の低下につながる場合があります。現金であればすぐ使えますが、不動産になれば売却に時間がかかり、固定資産税や管理費も発生します。保険に資金を移せば、解約しない限り現金化できません。借入をすれば利息負担が発生します。それぞれの策に伴うコストやリスクをきちんと計算に入れておかないと、「税金は減ったがかえって家計が苦しくなった」ということにもなりかねません。
節税対策ばかりに囚われ本末転倒にならないためのバランス
相続税を減らすこと自体は大切ですが、節税が目的化してしまうと本来の趣旨を見失います。財産は本来、ご家族の生活を豊かにするためのものです。節税のために無理な投資をしたり、大切な資産を手放したりして、家族が不利益を被っては本末転倒です。「なぜ相続税対策をするのか」を常に念頭に置き、ご家族にとって最適なバランスを追求しましょう。
専門家と十分にシミュレーションする重要性
相続税対策は複数の方法を組み合わせることも多く、その相互作用や将来的な税制変更の影響など、専門的な検討が必要です。そこで税理士など専門家の力を借りてシミュレーションを行うことが重要になります。
専門家に相談すれば、最新の税制に基づいたアドバイスを得られるだけでなく、「その対策をとることで別の税金(所得税や法人税)はどうなるか」「法的な問題はないか」といった総合的な視点での提案が受けられます。小田原市家族信託・相続相談所でも経験豊富な税理士が在籍し、お客様の状況に応じたオーダーメイドの相続対策プランを作成しています。プロと一緒に検討することで、より安心・確実な相続税対策が可能になるでしょう。
まとめ:自分の状況に合った相続税対策を選ぶために
生命保険、不動産、借入金、二次相続対策など、相続税を減らす方法は多岐にわたりますが、最も大切なのは「ご家族それぞれの状況に合った対策」を選ぶことです。資産規模や内容、家族構成、将来展望によって、効果的な策は変わってきます。
本記事で挙げた各策のメリット・デメリットを踏まえ、まずは現状分析から始めてみましょう。その上で必要であれば専門家に相談し、複数のプランを比較検討してください。小田原市家族信託・相続相談所では、地元の皆様に寄り添いながら最良の相続税対策を一緒に考えていきます。大切なご家族に負担を残さないよう、今のうちから適切な対策を講じておきましょう。
家族信託・相続のご相談は小田原市家族信託・相続相談所へ
生命保険の非課税枠や不動産活用、借入金による資産圧縮、二次相続対策など、相続税を減らすための様々な方法と注意点についてご紹介しました。小田原市家族信託・相続相談所では、これらの節税策の活用から家族信託による財産管理、生前対策の計画立案まで、ワンストップでご相談いただけます。相続税対策についてお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。