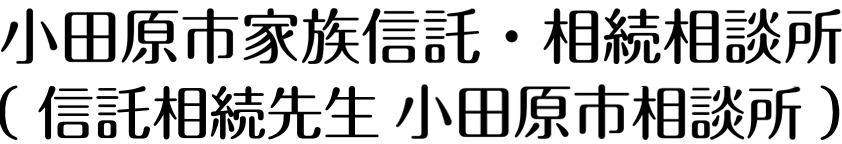生前贈与で賢く相続税対策:非課税枠の活用と注意点
- 公開日:
- 更新日:
はじめに
生前に財産を移転する「生前贈与」は、相続発生前に遺産を減らせるため、相続税対策の王道と言えます。特に毎年110万円まで非課税で贈与できる暦年課税制度の活用は、多くの家庭で実践されています。本記事では、生前贈与が相続税対策に有効な理由や具体的な方法、さらに制度を利用する上での注意点について解説します。暦年贈与の基本や、一度に大きな金額を渡せる相続時精算課税制度の概要、生前贈与の具体的な節税効果を紹介しながら、贈与を行う際の記録の重要性や税務上のルール(贈与から○年以内の加算など)についても説明します。効果的かつ安心な生前贈与による相続税対策のために知っておきたいポイントをまとめました。
生前贈与が相続税対策に有効な理由
生前贈与を活用すると、相続が発生する時点での財産そのものを減らすことができます。相続税は原則として死亡時点で保有している財産に課税されるため、生きているうちに財産を移してしまえば、その分だけ将来の相続税の対象が減るという仕組みです。
また、生前贈与は贈与を受ける人の数や贈与のタイミングによって節税効果が変わるのも特徴です。例えばお子さんが複数いる場合、それぞれに贈与すれば年間110万円の非課税枠を人数分活用できます。お孫さんなど法定相続人ではない親族にも贈与すれば、将来の相続人が受け取る遺産そのものを前もって減らすことにもつながります。さらに、早いうちから長期にわたって贈与を継続すればするほど、多くの財産を移転できるため節税効果は高まります。
つまり、生前贈与は「誰に・いつ・どれだけ贈与するか」の計画次第で、相続税対策として大きな威力を発揮します。特に親世代が比較的若いうちから始めれば、無理のない額を少しずつ移せるため、将来の相続に向けて着実に布石を打てるでしょう。
暦年贈与の基本(年間110万円の非課税枠を活用)
生前贈与で最も一般的なのが暦年贈与の活用です。暦年贈与とは、その年(暦年)ごとの贈与額に応じて贈与税を課す制度で、毎年1人当たり110万円までの贈与であれば贈与税がかからない仕組みになっています(基礎控除110万円)。例えば子や孫に毎年110万円ずつ贈与すれば、10年で1,100万円、20年で2,200万円の財産を無税で移転できる計算です。
暦年贈与のメリットは、受贈者(贈与を受ける人)ごとに毎年110万円まで非課税枠を使えることです。お子さんやお孫さんが複数いれば、その人数分だけ年間110万円枠を活用できます。また、110万円以下であれば贈与税の申告も不要なので、手続きが比較的簡単な点も利点です。
一方で押さえておきたいのが生前贈与加算のルールです。従来、被相続人の死亡前3年以内の贈与は相続財産に持ち戻す決まりでしたが、2024年からこの期間が段階的に延長され、最終的に死亡前7年以内の贈与が対象となりました。現状では、死亡前3年以内の贈与は全額、それを超えて7年以内(4〜7年前)の贈与は累計100万円を超える部分が相続財産に加算されます。つまり、亡くなる直前に駆け込みで行った贈与は、大部分が相続税の課税計算に組み込まれてしまうのです。
このため、暦年贈与による節税効果を十分に得るには、できるだけ早期から計画的に贈与を続けることが重要となります。例えば被相続人が健在でまだ元気な60代のうちから贈与を始めておけば、7年以上前の贈与は持ち戻しの対象外となり、確実に相続財産を減らせます。贈与を実行する際には、毎年贈与契約書を取り交わしたり、銀行振込で記録を残したりして「贈与が事実行われた証拠」をきちんと残しておくことも大切です(後述の注意点で詳述)。
相続時精算課税制度の活用方法
暦年贈与とは別に、相続時精算課税制度を利用してまとまった額を一度に贈与する方法もあります。この制度を選択すると、贈与税について年間110万円の基礎控除は適用されなくなりますが、代わりに特別控除として累計2,500万円まで贈与税が非課税になります(2,500万円を超える部分には一律20%の贈与税)。適用対象は、贈与者が60歳以上の親・祖父母、受贈者(贈与を受ける人)が18歳以上の子・孫などに限られます。
相続時精算課税制度を使うと、例えば子に2,000万円を一度に贈与しても贈与税はかかりません。その代わり、この制度を選択した贈与者からの贈与は全て相続時精算課税扱いとなり、将来相続が発生した際に贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。贈与時にかかった税(金額によっては超過分に20%課税)については相続税額から差し引いて精算する仕組みです。
この制度の利点は、住宅購入資金や事業資金など一度に大きなお金を渡したい場合に、2,500万円まで非課税で贈与できる点です。例えば、子夫婦がマイホームを建てる際に親が援助するといったケースで有効でしょう。また、2024年以降の改正で年間110万円までの贈与は相続時精算課税選択後でも申告不要で非課税とする緩和措置が導入され、使い勝手が向上しています。
ただし、相続時精算課税制度には注意点も多いです。一度選択すると、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せないため、少額贈与であっても全て申告が必要になります(110万円以下でも申告義務が生じる)。また、最終的には相続税の課税ベースに組み入れられるので、贈与による相続税の節税効果自体は原則としてありません。むしろ、制度を利用せず暦年贈与で少しずつ渡したほうが有利になるケースもあります。選択する際は制度のメリット・デメリットを理解し、税理士と相談の上判断することが大切です。
生前贈与を行う際の注意点
生前贈与は強力な相続税対策ですが、実施にあたっては以下のような注意点を意識しましょう。適切な手続きを踏まないと節税効果が損なわれたり、後日トラブルになる可能性があります。
贈与記録の重要性(贈与契約書や通帳管理)
生前贈与では、贈与の事実を証明できる記録を残すことが非常に重要です。具体的には、毎年贈与を行う際に贈与者と受贈者双方が署名押印した贈与契約書を作成し、金額や日付を明記して保管します。また、現金で手渡しするのではなく銀行振込などを利用し、通帳に振込記録を残すと確実です。このような書面や記録があれば、後日税務署から「本当に贈与したのか」と問われた場合にも証拠として提示できます。
記録を残しておかないと、贈与したつもりでも名義預金とみなされるリスクがあります。例えば、親が子名義の口座に毎年110万円ずつ預けていても、子がその口座の存在を知らなかったり使えなかったりすれば、それは実質的に親の財産と見なされる可能性があります。せっかく贈与しても相続財産に計上されてしまっては意味がありません。贈与契約書の作成と資金管理を徹底し、受贈者本人が自由に使える状態にしておきましょう。
駆け込み贈与のリスク(死亡前○年以内の贈与加算 等)
生前贈与加算のルールで述べた通り、駆け込み的な大量贈与にはリスクがあります。被相続人の体調が悪化してから急いで大きな額を贈与しても、現行制度では死亡前7年以内の贈与は大部分が相続税計算に持ち戻されてしまいます。特に死亡前3年以内の贈与は全額加算されるため、「最期に一気に子ども名義に変えれば税金ゼロ」というような都合の良い対策は通用しません。
これを避けるには、やはり早めにコツコツ進めることが肝心です。健康なうちから少しずつ財産を移しておけば、後になって「もっと早く始めていれば…」と悔やむリスクを減らせます。駆け込み贈与に頼らず、計画的に暦年贈与を活用しましょう。
贈与税申告の必要性と申告漏れ防止
毎年の贈与額が110万円を超えた場合には、贈与税の申告が必要になります。例えば1年間で子に200万円を贈与した場合、110万円を超える90万円分について贈与税申告を行い、所定の税額を納めなければなりません。申告期限は贈与した年の翌年2月1日から3月15日までです。
暦年贈与で毎年110万円以内に抑えていれば基本的に申告は不要ですが、教育資金の一括贈与特例や住宅取得資金贈与の非課税特例など、他の特例制度を使う場合や相続時精算課税を選択する場合は、別途申告が必要となるケースがあります。
申告漏れがあると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があるほか、税務署に贈与を把握されて相続時の調査につながる恐れもあります。生前贈与を確実に節税につなげるためにも、贈与税の申告が必要な場合は期限内に正しく申告・納税することを徹底してください。
まとめ(生前贈与を活用する際の賢い進め方)
生前贈与は相続税対策の大きな武器ですが、効果を最大限発揮するには計画性と正しい手続きが不可欠です。毎年の暦年贈与を早いうちから始めてコツコツ続けること、大口の贈与を検討する際は相続時精算課税制度も視野に入れること、そして何より贈与の事実を示す記録や適切な申告を怠らないことが重要となります。
小田原市家族信託・相続相談所では、生前贈与を含む相続税対策全般について税理士が親身にアドバイスしています。「どのくらいのペースで贈与すればいいの?」「贈与税の申告手続きが心配」といったお悩みにも丁寧にお答えします。賢く生前贈与を活用し、ご家族への円滑な財産継承と相続税の軽減を実現しましょう。
生前贈与のご相談は小田原市家族信託・相続相談所へ
毎年110万円の非課税枠を活用した生前贈与の方法や、相続時精算課税制度など生前贈与による相続税対策について解説しました。小田原市家族信託・相続相談所では、贈与計画の立案から贈与税申告、家族信託の活用まで幅広くサポートいたします。将来の相続に向けた生前対策をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。