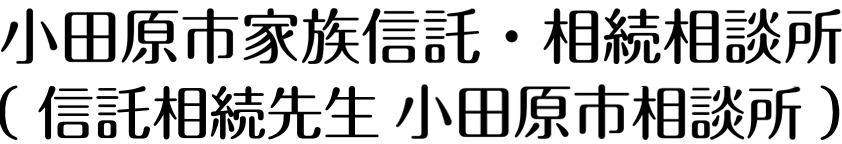相続税対策の基本:早めに知っておきたい生前対策のポイント
- 公開日:
- 更新日:
はじめに
相続が発生してから慌てて対策を講じても、時間が足りず十分な節税ができない場合があります。相続税対策は早めの準備が肝心です。本記事では、相続税対策の基礎知識と、生前にできる主な節税策について解説します。なぜ早めの対策が必要なのか、相続税の基礎控除額や税率といった基本から、生前にできる代表的な節税策まで幅広く紹介します。また、資産の把握や専門家への相談といった初歩のステップも解説しており、高齢の親を持つ方が今から知っておきたい相続税対策のポイントがわかります。早めに準備を始めるためのヒントが満載です。
相続税対策が必要な理由(早めの準備の重要性)
相続税は遺産の規模によっては高額になるため、事前の対策によって負担を軽減できる余地が大きい税金です。特に都市部では不動産価格が高く、思った以上に相続税が発生するケースもあります。例えば小田原市内でも、地価の上昇により自宅土地と預貯金を合計すると基礎控除額を超えてしまうご家庭が増えています。
相続税は累進課税(遺産額が大きいほど税率が高くなる仕組み)で、最大税率は55%にも達します。何も対策せずに放置すると、最悪の場合「遺産の半分以上が税金で持っていかれる」こともあり得ます。また、対策をしないまま親が高齢になり認知症になってしまうと、有効な財産移転が難しくなります。早めに相続税対策に着手することで、時間をかけて計画的に資産を移転でき、結果的に税負担を減らしやすくなるのです。言い換えれば、対策の開始が1年遅れるごとに節税の機会を失う可能性があると言えます。
相続税の基礎知識(基礎控除額・税率の仕組み)
効果的な相続税対策を考えるには、まず相続税の基本を理解しておきましょう。相続税には「この金額までは非課税」という基礎控除額があり、その計算式は以下の通りです。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば法定相続人(配偶者や子など)が2人なら基礎控除額は4,200万円です(=3,000万+600万×2)。遺産総額がこの額以下であれば相続税はかかりません。逆に言えば、対策の第一歩として「自分の家の遺産は基礎控除内に収まるか?」を把握することが重要です。
基礎控除を超える部分には相続税が課税されますが、税率は取得金額に応じて段階的に上がります。例えば課税価格が1,000万円以下なら税率10%、3,000万円以下部分は15%、5,000万円以下20%...という具合に最高55%まで累進します。各相続人が実際に払う税額は、一度相続税の総額を計算し、それを各人の取得割合に応じて按分して求めます。細かい計算方法は複雑ですが、大枠として「遺産が大きいほど高率の税がかかる」と覚えておきましょう。
なお、配偶者に関しては1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額まで相続税ゼロという特例(配偶者の税額軽減)があります。そのため多くの場合、夫から妻への相続では税金がかかりません。ただし、配偶者が多くの遺産を引き継ぐと、その後の二次相続(妻から子への相続)で税負担が増えてしまう可能性があります。この後の節税策の項目でも触れますが、一次相続で配偶者に集約しすぎないことも含め、二次相続まで見据えて計画することが重要です。
生前にできる主な相続税対策一覧
早めに取り組みたい代表的な相続税対策をいくつか挙げます。いずれも生前のうちに行うことで効果を発揮する対策です。親御さんが健在な今のうちから検討してみましょう。
暦年贈与(毎年110万円非課税の活用)
暦年贈与とは、1年間(1月1日~12月31日)に贈与した金額が110万円以下であれば贈与税がかからない制度を活用する方法です。贈与者一人につき受贈者ごとに毎年110万円まで非課税で贈与できます。例えば子や孫に毎年110万円ずつ贈与すれば、10年で1,100万円、20年で2,200万円の財産を無税で移転できる計算になります。
このようにコツコツ財産を移転することで、将来の相続財産を減らす効果が期待できます。ただし注意点として、生前贈与加算のルールがあります。2024年から、被相続人の死亡前7年以内の贈与に関する持ち戻し期間が延長されました。具体的には、死亡前3年以内の贈与は全額、4〜7年前の贈与は累計100万円を超える部分が相続財産に加算されます。したがって、亡くなる直前にまとまった贈与をしても、多くが相続税の課税対象に戻されてしまいます。
暦年贈与の節税効果を高めるには、できるだけ早い時期から毎年コツコツと贈与を続けることが肝心です。早く始めれば、7年以上前の贈与は加算対象から外れ、確実に相続財産を減らせます。贈与する際は贈与契約書を作成したり、振込など記録に残る方法で行ったりして、贈与の事実を明確にしておくことも大切です(後述の注意点参照)。
生命保険の非課税枠活用(法定相続人×500万円)
生命保険は相続税対策においてよく活用される手段です。死亡保険金には、「法定相続人の数×500万円」まで非課税になる枠があります。例えば相続人が配偶者と子2人の合計3人なら、500万円×3人=1,500万円までの保険金は相続税がかかりません。
現金で持っているとそのまま課税対象になる財産も、生命保険金として受け取れば一定額まで非課税になるため、預貯金を保険に充てておくだけで節税効果が得られる場合があります。また、保険金は遺産分割協議を経ずに受取人固有の財産として受け取れるため、相続発生直後の生活費や納税資金の確保にも役立ちます。
さらに、契約者や保険料負担者を工夫することで税負担を軽減できるケースもあります。例えば、子どもが契約者兼保険料負担者となり、親を被保険者、子どもを受取人とする契約にすると、支払われた保険金は相続税ではなく所得税(一時所得)で課税されます。一時所得には50万円の特別控除や税額1/2計算の制度があるため、場合によっては相続税より有利になることもあります。ただし契約形態によって税務上の扱いが複雑になりますので、実行する際は専門家に相談しましょう。
不動産への資産組み換えによる評価額引き下げ
現金などの流動資産を不動産に変えておくことで、相続時の評価額を下げられる場合があります。不動産の相続税評価額は、土地なら路線価または固定資産税評価額、建物なら固定資産税評価額で計算されるため、多くの場合、市場価格(時価)より低く抑えられます。例えば現金5,000万円をそのまま相続すると評価額5,000万円ですが、同額で購入した不動産の評価額が相続税上は3,500万円程度になるケースもあり得ます。
また、賃貸アパートや貸家付き土地などの賃貸物件を所有すると、建物には借家権割合の控除(30%減)、土地には貸家建付地の評価減(借地権割合に応じた減額)が適用されます。さらに、被相続人が居住していた宅地や事業用宅地には小規模宅地等の特例があり、一定面積まで評価額を50〜80%減額することが可能です。これらの制度を活用すれば、不動産を所有しているだけで大幅な評価減効果を享受できます。
ただし、不動産への資産組み換えは流動性の低下や管理コストの増加と表裏一体です。不動産は売却に時間がかかり、固定資産税や維持費も発生します。節税のために不動産を買ったものの、管理が大変だったり思うように賃貸収入が得られなかったりしては本末転倒です。物件選びや運用計画については十分に検討し、必要に応じて不動産や税務の専門家の意見を聞くようにしましょう。
二次相続まで見据えた遺産分割の工夫
相続税対策では、二次相続(配偶者から子への相続)まで見据えておくことが肝要です。一次相続(例えば父から母への相続)で配偶者が遺産を多く取りすぎると、配偶者の死亡時に子が相続する財産が膨れ上げり、トータルの税負担が重くなることがあります。
そこで、一次相続の段階で子どもにも適度に遺産を分配しておき、税額を平準化させる方法が考えられます。配偶者の税額軽減を使えば一次相続自体の税金はゼロにできますが、相続人が子だけになる二次相続では基礎控除額も下がり税率も上がる傾向にあります。例えば、一次相続であえて子に相続させて数百万円の税金を払ったとしても、将来の二次相続での課税財産が減ることで、総額では節税になる場合があります。
また、生命保険の活用でも触れたように、一次相続・二次相続それぞれで死亡保険金の非課税枠を使えるよう受取人を設定することも有効です。いずれにせよ、家族全体の長期的な視点で遺産配分を考えることが大切であり、この点も税理士など専門家とシミュレーションしながら検討すると良いでしょう。
相続税対策の第一歩(資産把握と専門家への相談)
いくつか代表的な相続税対策を紹介しましたが、実際に対策を講じるには現状の正確な把握が出発点となります。まず、ご自宅の不動産評価額や預貯金額、生命保険金額など、現在どれくらいの財産があるかを洗い出してみましょう。そして、それを基に相続税の簡易計算を行い、「このままだと相続税はいくらくらいかかりそうか?」を把握します。ここまでやって初めて、本格的な対策の必要性が見えてきます。
その上で、具体的な対策に移る際には専門家への相談を検討しましょう。相続税に詳しい税理士やファイナンシャルプランナー(FP)であれば、家族構成や資産状況に応じて適切な対策を提案してくれます。例えば、小田原市家族信託・相続相談所には相続対策に強い税理士が在籍しており、生前贈与の進め方や不動産活用のシミュレーション、家族信託の活用など幅広くアドバイスしています。専門家と一緒に検討すれば、自分たちに合った対策を安全に実行するためのロードマップが描けるでしょう。
まとめ(今日から始める相続税対策のススメ)
相続税対策は「いつかやろう」と先延ばしにせず、今日から始めることが重要です。暦年贈与しかり、生命保険しかり、不動産活用しかり、どの対策も時間を味方につけるほど効果が高まります。逆に、準備不足のまま相続が発生すると、もっと減らせたはずの税金を納めることにもなりかねません。
まずは現状把握からスタートし、できるものから少しずつ実行に移してみましょう。「何をしていいかわからない」という場合は、小田原市家族信託・相続相談所のような専門家の無料相談を活用するのも一案です。将来の安心のために、早め早めの相続税対策を心がけてください。
家族信託・相続のご相談は小田原市家族信託・相続相談所へ
相続税対策の基本と、生前にできる代表的な節税策について解説しました。小田原市家族信託・相続相談所では、生前贈与や生命保険の活用、不動産の有効利用や家族信託の導入など、お客様の状況に合わせた相続対策をご提案しています。相続税や贈与税、生前対策に関するお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。