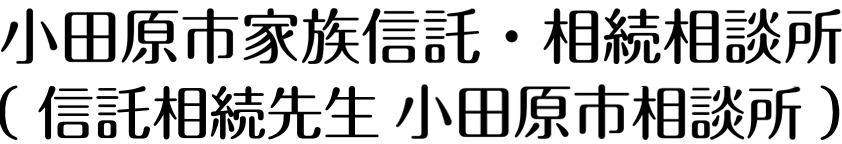未登記借地権と家族信託の実務Q&A
- 公開日:
- 更新日:
未登記の借地権でも家族信託は可能か。
未登記の借地権を信託財産とする家族信託は可能です。
ただし、その際には法律上の対抗要件の問題や地主の承諾取得など、いくつかクリアすべき課題があります。本記事では、専門家の視点から未登記借地権を信託財産とする家族信託についての疑問にQ&A形式でお答えします。借地借家法10条や信託法14条・34条の規定、地主承諾の実務など、押さえるべきポイントを一問一答で解説します。司法書士・弁護士・税理士・不動産実務家の方々に向けて、実務上役立つ知識とアドバイスをわかりやすくまとめました。
Q&A
Q1. 借地借家法10条による対抗要件とは何ですか?
借地借家法10条は、借地権の第三者対抗要件について定めた規定です。通常、土地の賃借権(借地権)は登記しなければ新地主など第三者に対抗できません。しかし実務上、土地賃借権の登記はほとんど行われないため、借地借家法10条が特別ルールを設けています。「借地権者がその土地上の建物を自己名義で登記して所有していれば、借地権は登記がなくても第三者に対抗できる」という内容です。つまり、建物の登記が借地権の存在を公示する役割を果たします。
家族信託では借地権者の地位が委託者から受託者に移るため、対抗要件を維持するには受託者名義で建物が登記されていることが必要です。信託設定後は速やかに借地上建物の所有権移転及び信託登記行いましょう。これによって、受託者(新借地人)が登記建物を所有している状態となり、信託後も借地権を第三者に主張できることになります。
ポイント
未登記借地権の場合でも、建物登記名義を適切に管理することで借地権の対抗力を確保できます。特に信託時に建物名義を受託者へ移すことが重要です。
Q2. 信託法14条は未登記借地権にどう関係しますか?
信託法14条は、信託財産に属することの第三者対抗要件を定めています。登記・登録が必要な財産(不動産や車など)については、登記等をしなければ「その財産が信託財産だ」と第三者に対抗できないという規定です。
問題は、未登記の土地賃借権(借地権)はこの登記を要する財産に該当するかという点です。
この点、学説では、登記を要するという説と、登記を要しないという説に見解が分かれています。
実務上、この論点には明確な結論が出ていません。ただ、受託者としては安全策を取るべきです。未登記借地権は信託登記そのものができないため、代わりに他の方法で信託財産であることを明確に示す必要があります。具体的には、建物に信託登記をして信託目録に借地権を記載する、信託契約書を公正証書にして権利移転の日付と内容を公証しておく、などの対応が考えられます。これらによって、「この借地権は信託財産に属している」という事実を第三者にも示しやすくなります。(完全とは言えませんが。)
ポイント
信託法14条の適用が不確実な以上、信託財産性を示すあらゆる措置を講じてリスクヘッジすることが求められます。
Q3. 分別管理義務(信託法34条)とは何? 未登記借地権の場合どうすれば?
信託法34条は、受託者に課される分別管理義務について定めています。受託者は、信託財産と自分自身の固有財産(および他の信託の財産)を混同しないよう管理しなければなりません。具体的には、登記・登録が可能な財産は信託登記・登録を行う、登記できない財産は物理的に分けて保管したり帳簿上明確に区分する、といった方法が求められます。
未登記借地権のように信託登記が事実上困難な場合、他の財産と混ざらないよう管理する工夫が不可欠です。例えば、地代の支払いや借地権上建物からの収入がある場合のように、借地権に係る収支は、信託口座にて明確に分別して管理することが考えられます。
分別管理を怠るとどうなるか、具体例で考えます。仮に受託者が自己の現金と信託財産の現金を一緒くたに持っていた場合、受託者の借金の差押えを受けた際に「その現金は信託財産だから差押えできない」と主張しても認められない可能性があります。信託財産だと証明できないからです。このような事態を防ぐためにも、分別管理義務を遵守することが結果的に信託財産を守ることになります。
ポイント
未登記借地権では、とりわけ分別管理義務の徹底が重要です。専用口座と帳簿管理で金銭の流れを明確化し、信託財産の証跡を残しましょう。
Q4. 家族信託のために借地権を譲渡するとき、地主の承諾は必ず必要ですか?
はい、原則必要です。 民法612条1項により、賃借権を第三者に譲渡するには地主(賃貸人)の承諾が必要とされています。家族信託で借地権が受託者に移転するのも法律上「譲渡」に当たるため、地主の承諾を得なければ契約違反となります。承諾なく譲渡した場合、地主は借地契約を解除できるとされています(民法612条2項)。
家族内で名義を変えるだけで実態は変わらないとしても、契約上は譲渡禁止特約の例外にはなりません。そのため信託契約を締結する前に、必ず地主に事情を説明して理解と承諾を得ましょう。
ポイント
地主の承諾は必須です。借地契約を解除され信託が意味をなさなくなる恐れがあるためです。
Q5. 地主の承諾書には何を記載すべき?
地主にはまず信託の目的や内容を丁寧に説明しましょう。例えば「高齢の親の財産管理のために信託を組む」「名義を息子に変えるが地代も利用状況も変わらない」等、地主にとって不安材料がないことを強調します。専門家が同席して説明するのも有効です。
承諾を得たら、口頭だけでなく書面(承諾書)を必ず作成します。承諾書には以下の点を盛り込むと良いです。
- 当事者の表示: 現借地権者(委託者)と新借地権者(受託者)の氏名・住所。
- 承諾内容の明示: 「借地権およびその上の建物を信託契約に基づき受託者に譲渡することを承諾する」旨。
- 包括承諾: 信託期間中の受託者変更や、信託終了に伴う委託者への名義復帰も承諾に含める文言。
- 契約条件不変更: 譲渡後も地代・契約期間など既存の借地契約条件は一切変更しないことの確認。
- 受益者の使用継続承認: 元借地人である受益者が引き続き建物に住む(使用する)ことを地主が認め、無断転貸に当たらないことの確認。
- その他特約: 建替えや抵当権設定(融資利用)の承諾に関する取扱い、承諾料の額と支払時期など。
こうした事項を網羅した借地権譲渡承諾書を地主から交付してもらえば、後々まで安心です。将来地主が代替わりしてもこの承諾書があれば、新地主に対しても承諾の事実を示せます。
ポイント
承諾書はできる限り詳細に作成し、信託による譲渡に関する取り決めを明文化しておきましょう。
Q6.承諾料はどのくらい払う必要がある? 値下げ交渉は可能?
承諾料(名義書換料)の相場は一般に借地権価格の10%前後と言われます。ただし、これはあくまで目安であり、地域の慣行や地主との関係によって変動します。都会の高額な借地権では10%でも莫大な金額になり得ます。
交渉による減額は可能です。家族信託の場合、「実際には親族間で管理を任せるだけで利用状況は変わらない」といった事情をよく説明すれば、地主によっては「それならそんなに承諾料はいらないよ」と理解してくれることもあります。実際に、「受益者(元借地人)がそのまま住み続けるなら今回は承諾料を免除する」というケースや、相場より大幅に低い金額で済んだ例もあります。
交渉のポイントは、地主にとっても損はないことを丁寧に伝えることです。新しく全く知らない第三者が入るわけではなく、これまで通りの人が住み、地代も滞らず払われるなら地主側にもリスクはありません。むしろ高齢の借地人に代わって子世代が管理する方が地代も確実だと安心材料になることもあります。
どうしても承諾料の負担が難しい場合は、任意後見契約や相続(遺言)による承継など他の手段も検討できますが、それらは信託ほど柔軟ではありません。多少譲歩してでも承諾を得て信託を実行する価値があるか、専門家と依頼者でよく話し合うと良いでしょう。
ポイント
承諾料は交渉次第です。家族信託の趣旨をしっかり説明し、地主の理解を得られれば減額・免除も可能性はあります。
Q8. 地主が承諾してくれない場合、どうすれば信託できる?
地主がどうしても承諾を拒む場合、借地借家法19条の裁判所許可を検討します。これは借地人が裁判所に申立てをして、地主に代わる譲渡許可を得る手続きです。裁判所は、譲受人となる受託者の資力や信用、地主が承諾しないことに正当な理由があるか等を審査し、必要に応じて承諾料の供託や地代の増額などの条件を付して許可を出すことがあります。
家族信託の場合も、「建物を第三者(受託者)に譲渡する場合」に該当するため、この非訟手続きを利用できます。ただし、裁判所手続には時間と費用がかかるうえ、必ず許可が下りる保証もありません。また、地主との関係も悪化しかねません。したがって、この裁判所許可制度は最後の手段と考えるべきでしょう。
専門家としては、できる限り任意の承諾を得るよう粘り強く交渉します。どうしても承諾料の点で折り合わなければ、例えば提示額を法務局に供託して許可を申請する、といった段取りになりますが、それでもまずは地主に「裁判所に申し立てる前にもう一度検討いただけませんか」と打診し、円満解決を目指す価値はあります。
ポイント
裁判所許可(借地非訟)は最終手段。地主との継続的関係を踏まえれば、使わずに済ませるのが望ましいです。
Q8. 信託を組成する際の全体的な手順を教えてください。
未登記借地権を含む家族信託を設計・実行する際の大まかな流れは次の通りです。
- 現状調査: 借地契約書や登記簿を確認し、借地権の種別(賃借権)、建物名義や借地権登記の有無を調べます。信託の目的・必要性(認知症対策・相続対策など)も整理し、関係者と共有します。
- 地主と事前協議: 信託の計画を地主に説明し、承諾の意向を確認します。承諾料や承諾条件について話し合い、合意点を探ります。
- 地主承諾書の締結: 地主から正式に承諾書を取り交わします。信託契約締結前に行い、書面を確保します。承諾料の支払いもこのタイミングで行います。
- 信託契約書の作成: 信託の目的、当事者(委託者・受託者・受益者)、信託財産(借地権・建物)、受益者の権利内容、信託期間、終了時の帰属先などを盛り込んだ契約書を作ります。内容が固まったら公正証書にするのがおすすめです。
- 登記手続き: 信託契約が発効したら、不動産の名義変更登記を申請します。建物の所有権移転登記(委託者→受託者)および信託の登記です。信託目録には借地権も信託財産とである旨を明記し、登記簿に反映されるようにしておきましょう。
- 信託財産の管理開始: 受託者が信託財産(金銭等)を引き継ぎ、信託専用口座への預替えや帳簿の作成を行うこと、地代支払い方法を信託口座からに切り替える、など実務対応をします。
- 信託期間中の運用: 受託者は信託目的に従い、借地権および建物を管理します。建物の修繕や建替え、賃貸借等必要な行為は信託契約と地主承諾書に照らして適切に実施します。定期的に受益者へ収支報告をし、信託財産の状況を透明化します。
- 信託終了時: 信託終了事由(受益者死亡など)が発生したら、借地権と建物を帰属権利者へ名義移転します。具体的には受託者から帰属権利者への所有権移転登記(信託抹消)を申請します。地主承諾書で包括承諾済みならそれを活用し、漏れていれば新たな承諾を得ます。最後に受託者が信託口座の残高を清算・分配し、報告を行って信託事務を完了します。
ポイント
事前準備から終了手続まで、各段階で法律に則った対応と丁寧な関係者調整が求められます。専門家は全体をコーディネートし、抜け漏れのないようサポートします。
Q9. 専門家として特に留意すべき点は何でしょうか?
専門家にとっての留意点をまとめます。
- 権利関係の正確な把握: 借地借家法や信託法、民法の関連条文を踏まえて理論武装し、依頼者や地主にわかりやすく説明する。
- 合意形成のサポート: 家族内での合意(受託者や受益者の役割理解)と、地主との合意形成に尽力する。特に地主には専門用語を避け、信頼関係を築く。
- 文書・証拠の整備: 信託契約書や承諾書、公正証書、登記完了証、帳簿、通帳など、後日の証拠となる書類をきちんと整備・保管するよう指導する。
- 税務・費用の検討: 登録免許税や公証役場手数料、信託終了に至るまでの各種税金など、費用について事前に試算し、依頼者に説明する。税理士等と連携し最適な形を検討する。
- プランBの用意: 万一信託が難航した場合に備え、任意後見や遺言など他の選択肢も視野に入れつつ助言する。ただし信託のメリット・デメリットを正確に比較し、依頼者が納得できる決断を支援する。
ポイント
専門家は法律知識だけでなく調整役としてのスキルも求められます。依頼者家族と地主双方に寄り添いながら、最善の解決策を導くことが大切です。
まとめ
未登記借地権を信託財産にする家族信託について、Q&A形式で主要な疑問点を解説しました。借地権の対抗力維持、信託法14条・分別管理への対応、地主承諾と承諾料といったキーポイントをご理解いただけたでしょうか。結論として、未登記借地権の信託は一筋縄ではいかない面もありますが、適切な法的措置と丁寧な実務対応で十分に実現可能です。
借地権という難しい権利を扱うからこそ、我々専門職の知識と経験が活きる場面と言えます。依頼者の大切な財産を守り、スムーズな承継をサポートするために、本稿で紹介した知見をぜひお役立てください。適切な手続きを踏めば、家族信託による借地権承継も法律の枠内で円滑に行えるでしょう。本記事が現場での判断・対策の一助となれば幸いです。